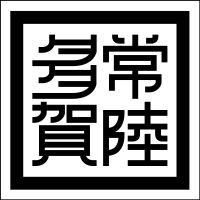 常陸多賀を元気にしたい!のコンセプトから生れた 「常陸多賀」マークプロジェクト オリジナルの「常陸多賀」ロゴマークを活用し、 各商店のオリジナル商品や販促物を制作する 多賀地区連合商店会の新たな街づくりプロジェクトです。 多賀街の商店のアイデアをお楽しみください! そして我が街の名産品としてご利用いただければ幸いです。 TMP95 たが・まあーく・ぷろじぇくと 95
↓画像をクリックすると、商品の詳細が表示します。 |
||||||
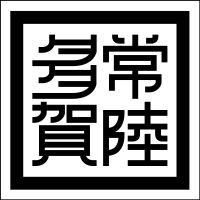 常陸多賀を元気にしたい!のコンセプトから生れた 「常陸多賀」マークプロジェクト オリジナルの「常陸多賀」ロゴマークを活用し、 各商店のオリジナル商品や販促物を制作する 多賀地区連合商店会の新たな街づくりプロジェクトです。 多賀街の商店のアイデアをお楽しみください! そして我が街の名産品としてご利用いただければ幸いです。 TMP95 たが・まあーく・ぷろじぇくと 95
↓画像をクリックすると、商品の詳細が表示します。 |
||||||
| 志お屋ホームページへ | | | 前へ戻る |
| 茨城県日立市千石町1-11-18 ℡ 0294-37-0408 FAX 0294-35-5583 営業時間:10:00~18:30(レンタルショップの最終受付は17:00になります。) 定休日:毎週木曜日・第2水曜日 |